ひき逃げ

ひき逃げの弁護内容
1 逮捕、勾留されないよう全力でサポートします。
事故の原因、態様、結果などが悪い場合、逮捕されたり、勾留をされたりする可能性があります。
しかし、逮捕・勾留をされれば、肉体的・精神的な不利益のみならず、仕事を休んだり、辞めなくてはならなかったりと、経済的・社会的な不利益を被ることになります。
弁護士がついていれば、逮捕前に警察に意見書やご家族の身元引受書、ご本人の誓約書などを提出することにより、逮捕をされないようにサポートします。
また、逮捕されてしまったとしても、身体拘束が必要ないことを主張して、早期の釈放を求めたり、その後に勾留決定がなされたりしないよう活動をします。
逮捕・勾留により、身体拘束がなされると、捜査機関から不正確な供述調書や実況見分調書を取られたりすることもありますので、逮捕されないようにしたり、早期の釈放を求めることは非常に重要です。
逮捕されないようにしたい、逮捕・勾留されてしまったけれど早期に釈放してほしいとお考えの方は、ぜひ私たちにご相談ください。
2 示談、嘆願書の取得を全力でサポートします。
ひき逃げでは、被害者に治療費や慰謝料などを支払い、示談をすることが非常に重要です。
ご本人様が任意保険に加入していれば、通常は、任意保険会社が示談交渉を代行してくれます。
しかし、保険会社の担当者の対応が悪い場合などは、被害者の被害感情を増幅することになりかねないので、弁護士が示談交渉をすることもあります。
保険会社が示談をしたとしても、示談書には加害者を「許す」という言葉は記載されていません。
そのため、別途、被害者から嘆願書をもらい、書面で「許す」という言葉をもらうことが非常に重要です。
また、通院期間が長期化した場合、示談が成立するまでに1年以上もかかる場合がありますので、その場合にも、示談に先立って嘆願書をもらうことが重要です。
示談をしたい、嘆願書をもらいたいと思っているけれども、どのようにしたらよいかわからない場合には、ぜひ私たちにご相談ください。
3 不起訴処分や略式裁判での罰金判決の獲得を全力でサポートします。
執行猶予付の判決の場合、万が一、執行猶予期間中に再度事故を起こした場合などには、執行猶予が取り消されて刑務所に行かなければならない可能性があります。
また、執行猶予付であっても、拘禁刑の判決がくだされると、公務員などの資格が失効して、職を失ってしまう可能性もあります。
そのため、ひき逃げを起こしてしまった場合、不起訴処分を獲得したり、略式裁判で罰金判決を獲得したりすることが非常に重要となります。
私たちは、そのために、事故の原因を解明し、具体的な再発防止策を策定し、反省の姿勢を示すことなどを通じて、不起訴処分・罰金判決の獲得を全力でサポートします。
4 事故態様に争いがある場合などには、各専門家と協力して原因を解明します。
事故態様に争いがある場合、ドライブレコーダーや監視カメラなどの映像や、車両の破損具合、信号サイクルなどから事故態様を解明する必要があります。
その場合、工学鑑定人などと協力して、各種証拠を分析し、事故態様を解明していきます。
5 正式裁判での起訴後も量刑が少しでも軽くなるように全力でサポートします。
正式裁判になった場合には、法廷で被告人質問や証人尋問が行われます。
ひき逃げで逮捕・勾留されていない場合には、事故から裁判まで1年以上かかることもあるため、事故時の記憶が薄れてしまうこともしばしばあります。
一方で、被害車両の目撃位置や衝突位置などを正確に証言しなければなりません。
その上、裁判で証言する場合は、緊張で頭が真っ白になってしまうこともしばしばあります。
そのため、事前準備を十分に行い、検察官の反対尋問についての想定の練習を行います。
また、情状証人を立てる場合には、情状証人の証人尋問の練習もしっかりと行います。
被害者対応の4つのポイント
1 嘆願書の獲得をサポートします。
私たちは、ひき逃げの刑事事件の場合、示談交渉はご依頼者の加入している保険会社が行うとしても、弁護人が直接謝罪を行い、被害者の処罰感情を少しでも和らげて、寛大な処分を裁判所に求める嘆願書を取得するサポートを行っております。
これが無ければ、被害者の事故直後の峻烈な処罰感情が書かれた供述調書のみが検察官や裁判官の目に触れることになり、重い処分・判決が出される要因となってしまいます。
そこで、弁護人からの謝罪に加えて、ご本人様やご家族からの直接の謝罪や反省文の作成、お見舞い等、被害者の処罰感情を和らげる方策を取ると共に、被害者にご依頼者様が更生するには寛大な処分が必要であることを丁寧に説明し、嘆願書を作成していただきます。
2 被害感情へ十分な配慮をいたします。
ひき逃げの被害者との示談交渉では、被害感情に十分に配慮しなければならないことはいうまでもなく、私たちは、被害者とアポイントを取る際や直接お会いする際には丁寧な対応を心がけております。
また、被害者の意見・要望をできる限りくみ取ることも大切です。
被害者のプライバシーに配慮する条項や被害者と加害者が接触しないことを約束する条項を盛り込んだ合意書の形で嘆願書を作成することもあります。
3 迅速な対応をいたします。
被害者との話合いにおいては、被害者の都合を考慮しながら、いつまでに嘆願書を取得する必要があるのか常に注意して迅速に進めなければなりません。
例えば、前科がつくことを回避したいというご意向であれば、検察官の起訴・不起訴処分の決定前までに嘆願書を取得する必要があります。
弁護士法人心では、できる限り、被害者が希望する日時に合わせて面会等の日程調整を行う等、迅速な謝罪等に向けて柔軟かつ迅速に対応することができます。
4 熱意ある対応をとります。
被害者から嘆願書を頂くためには、弁護士が熱意をもって交渉に臨むことが重要なポイントになります。
加害者の弁護人が被害者と交渉する際には、被害者の方からすれば、弁護人の言動を通じて加害者の反省を感じ取ることになります。
そのため、弁護人が熱意をもって対応すれば、被害者に対して、加害者が真に反省していることや加害者が被害回復に真摯に取り組んでいることをきちんと伝えることができます。
ひき逃げ事故発生からの流れ
事故発生から送検・勾留まで
ひき逃げ事故で逮捕された場合、すぐに弁護士と連絡をとることができます。
逮捕前にご相談いただければ、弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり、有利な結果となる可能性も高くなります。
依頼者が自首を希望する場合、法律上の自首の要件を備えていることを確認し、場合によっては出頭に同行することもあります。
逮捕された場合、逮捕から勾留までの間は、弁護士以外の者とは面会ができませんが、弁護士であれば、逮捕された方と面会できます。
家族や親しい方との連絡も、弁護士を通じて行うことができます。
逮捕後、勾留請求までの時間は極めて短いため、今後の対応策を大至急打ち合わせいたします。
逮捕後送検されると、検察は24時間以内に留置が必要かどうかを判断し、必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。
留置の必要なしとした場合釈放されます。
交通事故事件においては、勾留を防ぐことは十分に可能である事件が多くあり、証拠隠滅や逃亡のおそれが無いことを検察官や裁判官に説明するなどして、早期解放を目指します。
勾留された場合に備えて、身元引受人の確保、保釈保証金の準備等も行います。
起訴から裁判まで
ひき逃げは、昨今社会問題になっていることから、検察官は起訴する可能性が高いと思われます。
勾留されたままで起訴されると、勾留状態が続きますが、保釈請求も可能です。
保釈とは保釈金を収めることを条件として、一定の制限はあるものの、身柄の拘束が解かれる制度です。
保釈請求を行うと、裁判官が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。
保釈金は裁判手続の終了後、返還されます。
もし、保釈中に、裁判に出廷しない、証拠隠滅行為をするなど裁判官が定めた保釈の条件に違反した場合、保釈金は没取されます。
裁判が行われると裁判官により、有罪・無罪が検討され、有罪であれば量刑も言い渡されます。
起訴後は執行猶予付きの判決の獲得など、刑務所に入らずに済むための弁護活動が主となります。
ひき逃げを含む交通事故関連の事件では、具体的な事案や前科の有無等にもよりますが、執行猶予判決となることも多く、猶予期間内に執行猶予が取り消されなければ、刑務所に行かずに済みます。
自首したらどうなるのか

ひき逃げをしてしまった人が最初に検討するのは,自首をするか否かということでしょう。
さて,「自首」の定義とは,どのようなものであるかご存知でしょうか。
刑事ドラマやマスコミ用語では,例えば,警察が指名手配をして,それを知った犯人が警察に自ら出頭し,罪を打ち明けることをもって,「自首」としていることもあります。
しかし,これは,法律上の「自首」にはあたりません。
法律上の「自首」が成立するためには,罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に出頭する必要があり,その場合にその刑を軽減することができると定められています(刑法42条1項)。
「捜査機関に発覚する前」とは,犯罪の発覚前又は犯人の誰であるかが判明する前を意味し,この双方が判明しているが,犯人の所在だけが判明しない場合を含まないとされています。
「自首」は,必ずしも犯人自らする必要はなく,他人を介して自己の犯罪を捜査機関に申告したときも有効です。
要するに,犯罪または犯人が警察等の捜査機関に発覚する前に,捜査機関へ犯罪事実を打ち明ける必要があることがあります。
法律的な「自首」にあたるためには,思っていた以上に,要件が厳しい,と感じた方も多いのではないでしょうか。
また,「自首」の効果についても,その刑を軽減することができるという裁量的減軽になっているため,自首したからといって条文上は必ずしも刑が減軽されることが保障されていません。
これだけですと,ひき逃げをした者が自首することには意味がないのではないか,と感じた方もおられるかもしれません。
しかし,やはり,自首をすることは事件の早期解決につながり,被害者の救済にも資することになりますし,なにより罪を犯した人の反省と更生につながると考えられますので,刑を決める上で,非常に大きな考慮要素となります。
その意味では,仮に,法律上の自首にあたらなくとも,自ら罪を認めてそれを潔く申告する態度は,刑の重さを決めるにあたり,裁判上非常に重視されるといえます。
また,捜査機関である検察が,起訴・不起訴を決めるにあたっても非常に重視しています。
犯罪を打ち明けることは,大変勇気のいることですが,犯してしまった罪に真摯に向き合う態度が,更生への第一歩であるため,勇気ある行動それ自体が評価されるべき出来事ととらえられているといえます。
では,ひき逃げをしてしまったことを捜査機関に告白する前に,弁護士に相談することに意味はあるのでしょうか。
ひき逃げについて自首をした場合,その場で事情を話し,警察が供述調書することになります。
しかし,何を話すのか,供述調書に署名捺印をすべきか,供述調書に誤りがあった場合どう対応するのかなど,事前に知っておくべき情報がたくさんあり,事前に弁護士に相談してアドバイスをもらうことは有益です。
また,事案によっては,自首の後,逮捕されてしまうこともありますが,事前に弁護士に刑事弁護を依頼しておけば,逮捕後,速やかに身体解放に向けた弁護活動を開始できます。
社会内での更生が十分可能であることを正確に理解してもらうために,ひき逃げについて「自首」を検討する際に弁護士に相談することには,非常に大きな意味があると思います。
弁護士法人心では,所属弁護士のそれぞれが,得意分野をもっており,刑事事件を得意分野としている弁護士も所属しております。
東海地区でひき逃げをしてしまい自首をしようか悩みを抱えている方は,弁護士法人心 名古屋法律事務所まで,まずはご相談ください。
刑罰の種類
1 刑法における刑罰

刑罰の種類は主に5種類あり、刑法第九条で「死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。」と定められています。
また、それぞれの刑罰は、
財産刑・・・罰金、科料
自由刑・・・拘禁刑、拘留
生命刑・・・死刑
に区分されます。
2 主刑
⑴ 死刑
「死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。」と定められています。
死刑が選択される基準としては、犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性、残虐性、結果の重大性、特に殺害された殺害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等から判断されます。
抽象的な表現として「極刑」あるいは「処刑」とも表現されます。
⑵ 拘禁刑
「拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。拘禁刑は、刑事施設に拘置する。拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。」と定められています。
拘禁刑とは、有罪判決を受けた者を刑務所に拘禁し、改善更生を図るために必要な作業や指導を行う刑罰です。
現在の日本の刑罰の中でも、拘禁刑は死刑に次いで重い刑罰です。
特に無期拘禁刑に関しては、仮釈放がされない限り、刑務所に収容されるとても重い罪となります。
拘禁刑が3年未満で、よい情状がある場合には、執行猶予が付されることもあります。
実務上は、執行猶予は3年、4年、5年のどれかが選択されることが多いです。
⑶ 拘留
「拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。」と定められています。
拘禁刑は、刑務施設に収監される自由刑です。
違いは、拘束期間の長さで、拘留は三十日未満と、短期の期間が設定されます。
⑷ 罰金
「罰金は、一万円以上とする。
ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。」と定められています。
財産刑のひとつで、罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置されます。
⑸ 科料
「科料は、千円以上一万円未満とする。」と定められています。
罰金に同じく財産刑のひとつですが、違いはその金額です。
罰金は1万円以上とするのに対し、科料は1万円未満とされています。
科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置されます。
3 付加刑
付加刑の没収は、犯罪に使われた物、犯罪で得たものなどを国が取り上げるというものです。
付加刑とは他の刑罰と一緒に処罰されることで、没収刑のみ単独での刑罰はありません。
4 ひき逃げの場合
ひき逃げの場合は、拘禁刑か罰金刑となります。
ただし、ひき逃げは、被害者が負傷や死亡しているので、特に有利な情状がない限りは、拘禁刑になる可能性が高いです。
そして、近年のひき逃げ犯に対する処罰感情の高さから、ひき逃げをした場合、執行猶予がつかず、実刑判決になる可能性も十分にあります。
名古屋でひき逃げの刑事事件についてお悩みの場合は、弁護士法人心 名古屋法律事務所に所属する弁護士にご相談ください。
全力でひき逃げの刑事弁護をさせていただきます。


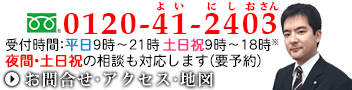
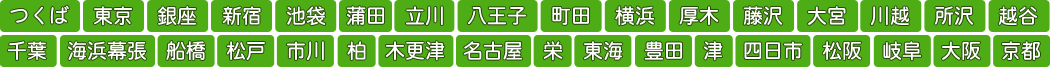
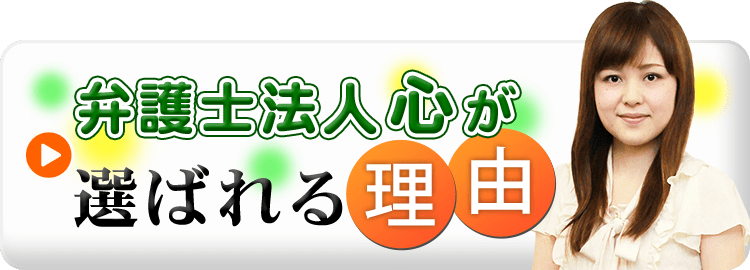







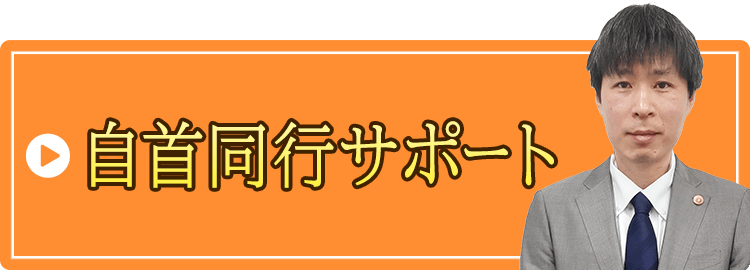





ひき逃げ事件の概要
ひき逃げとは、人身事故や死亡事故を起こした者が、被害者の救護や警察への報告などをしないまま、現場を立ち去ることをいいます。
そして、ひき逃げをすると、3種類の責任が発生します。
①民事責任
ひき逃げも人身事故、死亡事故の1類型ですので、被害者やご遺族に対して、損害賠償責任を負います。
そして、ひき逃げという行為により、より大きな精神的苦痛を被ったとして、慰謝料などを増額して請求される可能性もあります。
②行政上の責任
ひき逃げにも、救護義務違反、報告義務違反などの類型がありますが、この内、最も重い救護義務違反の場合、違反の点数は35点となります。
そのため、ひき逃げの原因となった事故の態様のいかんに関わらず、原則として、免許取消処分となります。
もっとも、事故を起こしたことを知らなかった事情や、ひき逃げに至った事情を弁解すれば、行政処分が減軽される可能性もあります。
弁護士法人心では、意見の聴取手続に代理人として同行し、事情を説明して、行政上の処分が少しでも軽くなるような弁護活動を行います。
③刑事責任
事故を起こした場合、㋐負傷者の救護と危険防止の措置を取る義務、㋑警察に事故報告する義務、㋒現場に留まる義務が発生します。
そして、それぞれの義務を怠ると、刑事罰が取られます。
㋐負傷者の救護と危険防止の措置を取る義務違反は、事故が運転者の運転に起因する場合は10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、そうでない場合は5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となります。
㋑警察に事故報告する義務違反は3か月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金、㋒現場に留まる義務違反は5万円以下の罰金となります。
いずれについても、人身事故や死亡事故を起こして、ひき逃げをしてしまうケースでは、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪とあわせた刑罰となりますので、前科などの情状によっては、実刑判決もあり得えるため、より適切な弁護活動が必要となります。